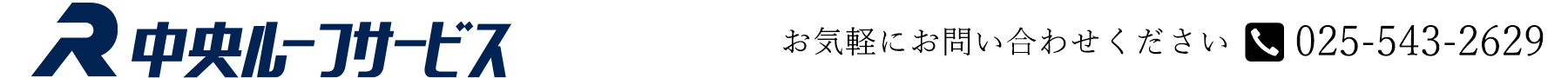弊社はこの度、建設分野においてもSDGsを進めて行くことを目指して作られた「新潟県SDGs推進建設企業登録制度」に登録いたしました。
我々が扱っております「瓦」は長い寿命を持ち、何度も再使用が出来る高い環境性能を有しています。この性能を生かし、既存の瓦を用いて葺き替える「葺き直し」の普及を進めて行くことで、環境対策に貢献して行きたいと考えております。
「もったいない精神」でまだ使えるものを生かし、廃棄物も減らして行きます。これが我々の活動のメインになります。
下に、「新潟県SDGs推進建設企業登録制度」のポータルサイトのQRコードを載せておきますので訪れてみて下さい。